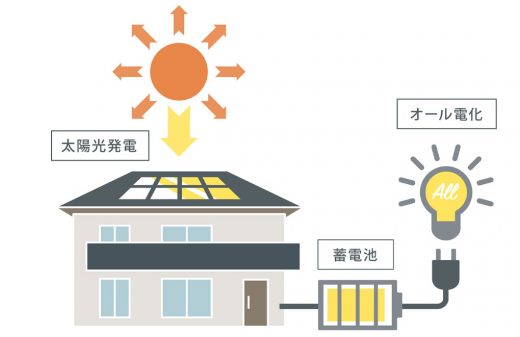2021.04.08
帰国子女パパならではの「学び」や「ライフスタイル」は? 第2回 「男家系だからこそ、花のある生活を」

現在、僕は妻と長男6歳と次男4歳と東京で暮らしていますが、11歳から18歳までをアメリカ・カリフォルニア州のサンディエゴという街で過ごしました。サンディエゴは人種のるつぼのような街で、異なる文化背景を持つさまざまな民族がともに暮らしています。そんな街で多感な思春期を過ごした僕は、よく「見た目は日本人だけど中身は外人だね」といわれます。そのことに否定はしませんが、だからこそ、見えてくることや思うことはたくさんあります。今回は、そんな僕のちょっとひねくれた目線で『花のある生活』について紹介していきます。
INDEX
花が嫌いな女性はいない
断言します。花を贈られて嫌な気分になる女性はいません。もちろん、ときと場合にもよりますが、誕生日や記念日のプレゼントでも、なんでもない日のサプライズ(むしろこれが効果的!)でも、お花をもらって嫌な気分になる女性はいないでしょう。ある意味、プレゼントの「正解」といっても過言ではないですね。
でも、日本では日常的に誰かに花を贈るという行為はまだまだ浸透していない気がします。キザだとか、照れくさいとか……。もちろん、その気持ちもわからなくもないのですが、正解が分かっているのに手を上げない意味が分からない! と僕の中のガイジンがいっています(笑)。
僕がまだアメリカにいたころ、当時、通っていた高校の先生が「男たるもの、肝心なときはまず花束を持ってひざまずく! それがスタートラインだ!」と話していて、思春期の僕にはとても印象的でした。
語弊のないようにしたいのですが、異性にモテるために花を好きになれ、といいたいわけではありません。なぜ、花が嫌いな人はいないのか。花の何がそんなに魅力的なのか。それは女性だけでなく、きっと男性も同じはず。このコロナ禍の1年、あらためて花の魅力に気付いた方も少なくないのではないでしょうか。
ベランダのミモザに救われた自粛期間

2020年の自粛期間中、我が家のベランダで育てていたミモザが花を咲かせました。世の中(どころか世界中)が未曾有の感染症ウイルスに驚き、困惑する中、その情勢を嘲笑うかのように、それはそれは美しい花を咲かせたのです。その華麗さは今でもはっきり覚えています。
外出がままならない時期、窓の外を見るとベランダに黄色いミモザ。その美しさにどれだけ心が救われたか。その出来事は僕だけではなく、子どもたちにもより鮮明に、かつ強烈に刻まれたようです。というのも、いつもは保育園や公園などで走り回っていた長男にとって、自粛期間中、ベランダは1日の大半を過ごす遊び場だったので、その場をきれいに彩るミモザは春に咲く花として、桜以上の存在になったようでした。
花をもらって嫌な気分がしないのは、花がきれいだから。もちろんそうなのでしょうが、じゃあ、なんできれいだと感じるのかというと、生命力に満ち溢れていて、同時に季節(もしくは自然)を感じるから。それが人間の心をぽっと温めてくれるからなのでしょう。
ベランダのミモザを少しだけ切って、ダイニングテーブルに飾ったとき、部屋の雰囲気が一瞬で変わったと感じたこと、それを子どもたちと共有できたことは、とても価値があったと思っています。
季節を感じられる「きっかけ」を作ろう

花は元気を与えてくれる。季節の訪れを教えてくれる。ちょっと大げさですが、生きることの喜びを感じさせてくれる。だから、もらうと嬉しい。すごく当たり前なことなのかもしれませんが、それはたぶん、世界共通のことなのです。そして、これからその共感力はより強まっていくと思います。
だからこそ、季節を感じられる場所を住まいに作ることは大切な気がしています。僕にとって、それはベランダ。今はミモザのほかにもたくさん草花を育てています。もし、家の中にそのような場所がなかったとしても、近くの花屋さんで季節の花を一輪買ってきてダイニングテーブルに飾るだけでもいい。肩肘張らず、店員さんに気軽に「旬な花を一輪ください」といえばいいのです。僕は子どもたちを連れて近所の花屋さんによく行くのですが、子どもたちには店員さんとよく話をさせるようにしています。花と精神的な距離を縮めることは、将来、必ず役に立つはずだから(いろんな意味で!)。そして、彼らが中学生ぐらいになるころには、「いいか、男たるもの、肝心なときはまず花束を持ってひざまずけ! それがスタートラインだ!」と伝えたいと思っています。
住まいに積極的に花を取り入れることは、生活に彩りを与えるだけではなく、子どもたちの感性を育む上でもとても好ましいことだと思います。住宅展示場では、プロによる花の生け方や飾り方のアイデアや工夫がたくさん見られます。実際にそれらを見ながら、みなさんにとって心地いい花のある暮らしを楽しんでみてくださいね。
執筆・情報提供

引地海
11歳から18歳まで米カルフォルニア州サンディエゴで過ごす。大学卒業後は広告代理店にてファッションや美容クライアントのメディアプラニングに従事。その後、企画会社を経て、2014年に長男誕生にあわせて独立。現在もフリーランスの編集者として企画、メディアプロデュース、イベントの演出、 PRなど幅広く活動中。
Ⓒ2020 Next Eyes.co.Ltd
この記事はネクスト・アイズ(株)が提供しています。