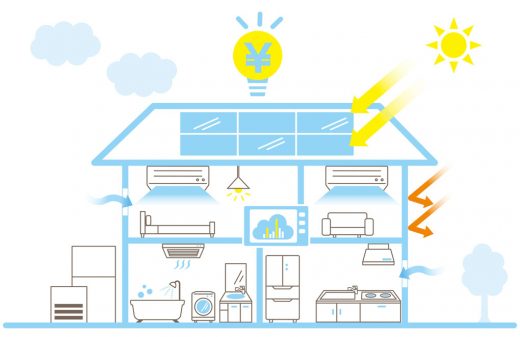2025.01.08
2025年度最新版 税制改正大綱|住宅税制が明らかに!住宅ローン減税は継続へ
シリーズ:税制改正大綱

2025年の税制度の方向性を決める「2025年度与党税制改正大綱」が、2024年12月20日に決まりました。例年よりも2週間ほど遅い決定となった要因は、所得税の控除額の引き上げ幅を巡って、与野党間で協議が続いていたためです。
では住宅計画をお持ちの方が気になる住宅税制の変更点は、「変更なし」といえるでしょう。拡充もなければ、縮小もない。ただし、性能の高い住宅を取得する子育て世帯に対しては手厚い支援が継続されているため、税制面だけを考慮すれば「住宅の買い時が続いている」といえます。
INDEX
2025年度の与党税制改正大綱が決定、改正までの流れは?
自民党と公明党は2024年12月20日、令和7年度(2025年度)の与党税制改正大綱を決定しました。税制改正大綱は、これからの税の方向性を示したもので、増税や減税、優遇措置の継続、廃止などが明記されています。
基本的には、政府(内閣府)の税制調査会が中長期的視点から、おおまかな税のあり方や方向性を検討し、1年ごとの短期的な具体案は与党が検討しとりまとめます。具体案は、毎年夏頃までに各省庁などからの要望を踏まえて、与党税制改正大綱に組み込まれています。
与党税制改正大綱の決定後は、速やかに閣議に提出されます。閣議では、内閣総理大臣と国務大臣の全会一致によって決定(閣議決定)し、財務省などが大綱に基づき改正法案を作成。改正法案は、国会に提出され、衆議院や参議院の審議を経て、本会議で可決されると、法案に定められた日から新たな税制が始まります。
ただし、自民党と公明党は現在、与党ですが過半数割れとなっており、そのため、国会審議の過程で内容が変更される可能性がありますので今後の動向はご注意ください。
住宅ローン減税は継続、借入限度額は現状維持
それでは、気になる住宅関連の税制について、与党税制改正大綱から抜き出して紹介しましょう。高額なローンを組んで新築住宅を建てようと考えている人が最も気になる制度が「住宅ローン減税」だと思います。
住宅ローン減税制度は、省エネ性能の高い住宅とその敷地となる土地を取得する際に金融期間などから借り入れた住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除します。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除されます。
2025年度与党税制改正大綱では、子育て世帯への支援として、「子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充」という項目などが盛り込まれました。
引用:2025年度与党税制改正大綱17ページ参照
内容は、「2024年限りの措置として対応した上乗せ措置について、2025年限りの措置として講ずる。所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から控除し、個人住民税の減収額は、全額国費で補填する」というものになります。
つまり、2024年の住宅ローン減税制度が2025年も継続し、活用できるということです。2024年限りの上乗せ措置とは、子育て世帯と若者夫婦世帯を対象とする「新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については1000万円の借入限度額の上乗せ措置」となります。
また、2024年度税制改正大綱には、「子育て世帯においては、住宅取得において駅近等の利便性がより重視されることを踏まえ、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1000万円以下の者に限り40㎡に緩和する」との文章も明記されており、この制度も同様に1年間延長となります。
これらを整理すると、2025年の住宅ローン減税の内容は、以下の通りです。
2025年の住宅ローン控除
※太字が2025年税制改正内容
| 住宅の性能区分・世帯別 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年入居 | 2025年入居 | ||||
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4500万円 | 0.7% | 13年間 | 409.5万円 | |
| 子育て世帯・若者夫婦世帯※ | 5000万円 | 455万円 | |||
| ZEH水準省エネ住宅 | 3500万円 | 318.5万円 | |||
| 子育て世帯・若者夫婦世帯※ | 4500万円 | 409.5万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 3000万円 | 273万円 | |||
| 子育て世帯・若者夫婦世帯※ | 4000万円 | 364万円 | |||
| その他の住宅 | 0円 | – | – | – | |
- ※ 「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
- ※ 所得要件は2000万円以下
- ※ 床面積要件は50㎡以上。合計所得金額1000万円以下の場合は40㎡以上に緩和
- ※ 所得税から控除しきれない額は個人住民税額から控除
制度の対象者は、若者夫婦世帯(夫婦どちらかが40歳未満)、子育て世帯(19歳未満の子どもを育てる)に限ります。住宅は、新築だけでなく買取再販住宅も対象です。築古の住宅を住宅事業者が取得し、増改築や省エネ性能向上リフォームなどを施した住宅を購入する場合も、住宅ローン減税制度が活用できます。
また、東日本大震災の被災者などが新たに上記の住宅を取得する場合、借入限度額は一律5000万円に拡充されています。
住宅ローン減税制度は、1986年度から続く減税による住宅取得支援制度ですが今回の税制改正大綱でも盛り込まれている通り、毎年見直される制度です。今回は、2024年の内容が引き継がれましたが、2026年も現状水準の支援が続くという保証はありません。優遇措置が活用できる2025年の住宅購入を検討してもいいかもしれません。
なお、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン減税の対象外となりますので注意が必要です。
固定資産税の減額措置や贈与税非課税措置も活用可能
一方、検討事項として「新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置については、社会経済の情勢などを踏まえ、安全安心な住まいの実現など住生活の安定の確保及び向上の促進に向け国として推進すべき住宅政策との整合性を確保する観点から、地方税収の安定的な確保を前提に、そのあり方について検討する」(与党税制改正大綱111ページ)との文言が盛り込まれています。
固定資産税の減額措置は、住宅価格が上昇する環境下で住宅取得者の初期負担を軽減するための特例措置です。新築戸建住宅は3年間、マンションは5年間、税額を2分の1に減額します。さらに長期優良住宅の場合は減税期間を2年間延長し、戸建住宅は5年間となります。国土交通省の資産によると、2000万円の住宅を新築した場合、3年間で約27万円の負担軽減効果が期待できるとのことです。
固定資産税の減額措置は、2024年の税制改正で現行措置の2年間の延長(2026年3月31日まで)が決定しています。見直されるとすれば、次(2026年度)の税制改正大綱となります。
さらに、2024年度の税制改正で3年間の延長が決まった「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」も活用できます。
この制度は、質の高い住宅の普及と快適な暮らしの実現を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築や取得、増改築のための資金を贈与された場合に、一定額までは贈与税が非課税になる制度です。現行制度の適用期限は2026年12月31日となります。
贈与税非課税限度額は、ZEH水準の住宅が1000万円、その他の一般住宅が500万円。いずれの住宅も床面積50㎡以上が要件となります。
今回、紹介した制度は多くの住宅取得検討者が活用できる主な支援制度です。このほかにも、長期優良住宅であれば適用できる減税制度(不動産取得税、固定資産税、登録免許税など)もあります。政府は、良質な住宅を普及させるため、省エネ性能が高く、長寿命な住宅に対する補助・支援策を充実させています。
皆さんが取得・検討している住宅では、どのような支援策が活用できるのか、ハウスメーカーの担当者にじっくり相談してみてください。
SERIES税制改正大綱
情報提供

>>住宅産業新聞社サイトへ
© Housing Stage All rights reserved.